企業の経営者や人事部の皆さま、同一労働同一賃金への対応はお済みですか?
見直しが必要だとわかっていても、具体的な対応策がわからず、お困りの企業も多いでしょう。
この記事では、同一労働同一賃金の対象者や具体的な対応策について解説します。
行政による指導強化が進められているため、この記事を読んで早急に点検・対応をしてください。
<目次>
■同一労働同一賃金とは
■同一労働同一賃金の適用範囲
1.短時間労働者(パートタイム労働者)
2.有期雇用労働者
3.派遣労働者
■企業が守るべき3つの規定
1.不合理な待遇差をなくすための規程の整備
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
■対応を見直す際のポイント
1.厚生労働省のガイドラインやマニュアルを活用する
2.労使で十分な話し合いを行う
3.計画的に対応する
■企業への行政指導が強化
■不合理な待遇差をなくし誰もが働きやすい環境を
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金とは、2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」の取り組みの一つです。
従業員の処遇に関して、同じ仕事をしているなら同じ処遇に、仕事に違いがあるなら、違いを明確にしたうえでバランスの取れた処遇にする必要があります。
正社員とそのほかの従業員の間に生じる、不合理な待遇差の禁止を目的としたものです。
同一労働同一賃金の適用範囲
同一労働同一賃金の対象となる「非正規雇用労働者」の範囲と、対応が必要な待遇差の例を3つ紹介します。
1.短時間労働者(パートタイム労働者)
労働時間の長さだけを理由に、正社員と比べて短時間労働者に対して不合理な扱いをしてはいけません。
具体的に見直しが必要な格差は、以下のような例です。
例:「パートタイム労働者だから」と、通勤手当が支給されない
業務内容などの違いから手当が対象にならない合理的な理由がない限り、是正が必要です。
2.有期雇用労働者
雇用期間のみを理由に、正社員と比べて有期雇用労働者に対して不合理な扱いをしてはいけません。※有期雇用労働者とは1年などの期間を設けた労働者。契約社員など。
具体的に見直しが必要な格差は、以下のような処遇です。
例:「有期雇用労働者は賞与の対象にならない」
賞与の性質や有期雇用労働者の業務内容などから、説明可能で合理的な理由がなければ差別的な扱いは禁止されています。
3.派遣労働者
同一労働同一賃金は、派遣労働者に対しても適用されます。
派遣労働者の身分を理由に、正社員と比べて短時間労働者に対して不合理な扱いをしてはいけません。
例:派遣労働者は正社員ではないから休憩室や更衣室の利用を制限する
上記のような利用制限がある場合、是正が必要です。
企業が守るべき3つの規定
同一労働同一賃金に取り組むにあたり、具体的に企業に義務づけられている3つの規定を解説します。
事業規模にかかわらず全ての企業が対象になるため、必ず確認してください。
1.不合理な待遇差をなくすための規程の整備
基本給・賞与・手当など、あらゆる待遇について、正社員と非正規雇用労働者との間に不合理な差を設けてはいけません。
格差が不合理であるかの判断は、「均衡待遇」と「均等待遇」の2つのポイントで判断されます。
|
均衡待遇 |
職務内容や配置変更の内容などに応じた、バランスの取れた待遇 |
|
均等待遇 |
職務内容や配置変更の内容が同じ場合、まったく同じ待遇 |
職務内容等に違いがないなら同じ待遇に、違いがあるなら違いに応じてバランスの取れた待遇にする必要があります。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者から求めがあった場合、正社員との待遇差の内容や、待遇差が生まれる理由を説明する義務があります。
「パートだから」といった差別的な理由や、「期待値が違うから」などの主観的で曖昧な説明では不十分です。
また、説明を求めた非正規雇用労働者に対して、不利益取り扱いをしてはいけません。
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
これまで規定のなかった有期雇用労働者に関する行政から企業への助言・指導等に関して、規定が明文化されました。
違反がみられる場合などに、行政指導を受ける可能性があります。
また、均衡待遇や正社員との待遇差の内容・理由に関する説明について、裁判外紛争解決の申し立てが可能です。
申し立ては、事業主・労働者の双方から行えます。
都道府県労働局が、無料・非公開で紛争解決を援助してくれます。
対応を見直す際のポイント
同一労働同一賃金を推進するにあたり、まずは自社の処遇制度の点検が大切です。
自社が同一労働同一賃金に適した制度になっているか、見直す際のポイントを3つ解説します。
1.厚生労働省のガイドラインやマニュアルを活用する
自社の制度点検には、厚生労働省が提供しているガイドラインや、点検・検討マニュアルを活用しましょう。
業界別のマニュアルも準備されているため、自社にあった内容を使用してください。
ワークシートの項目を記入しながら、同一労働同一賃金の取り扱いができているもの・できていないものを洗い出しましょう。
参考:厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)」
2.労使で十分な話し合いを行う
処遇の見直しを行う場合、労働者の意見も適切に反映し、労使双方が納得できる改善となるよう十分な話し合いが必要です。
就業規則の変更をともなう場合は、労働者代表への意見聴取が義務付けられているため、必ず意見聴取をして意見書を提出してもらうよう注意してください。
制度変更の過程でも、正社員・非正規雇用労働者で不合理な区別をせず、誠実な対応が大切です。
3.計画的に対応する
実際の制度変更は、関係各所で協議して計画的に実施してください。
処遇の改善や施設の利用ルールの変更を行う際、原資の確保が必要になる場合がほとんどです。
資金面などの課題からすべての格差を一斉に改善できない場合も多いため、企業の実情に合った現実的な計画が大切です。
企業への行政指導が強化
同一労働同一賃金について、行政から企業への指導強化が始まっています。
企業は、これまで以上に迅速な対応が必要です。
2022年12月、同一労働同一賃金の徹底に向けて、都道府県労働局と労働基準監督署の連携強化に関する方針が発表されました。
労働基準監督署による定期監督の際に、不合理な待遇差の有無についても確認されるようになります。
また聞き取り調査結果は都道府県労働局にシェアされ、違反の恐れのある企業に報告徴収を実施します。
同一労働同一賃金への迅速な対応が急務といえるでしょう。
不合理な待遇差をなくし誰もが働きやすい環境を
同一労働同一賃金の実現は、すべての労働者が公平に評価され、処遇されるための重要な下地です。
業務内容に応じた適切な処遇は、労働者の勤労意欲を上げ、離職の防止や業績向上などの効果が期待できます。
同一労働同一賃金の実施に向けて、まずは自社の制度の点検・見直しから始めてください。
従業員の意見を取り入れながら、誰もが公平・公正に働ける職場作りを目指しましょう。
Q1.同一労働同一賃金の対象となる「処遇」とは、賃金に関する事項のみでしょうか?
対象となる処遇は、基本給や手当、賞与などの賃金のみに限られません。
スキルアップのための教育機会や、休憩室や更衣室の利用などの福利厚生も「処遇」に含まれます。
Q2.同一労働同一賃金の推進をサポートしてくれる、公的な機関はありますか?
「働き方改革推進支援センター」を活用しましょう。
働き方改革推進支援センターは47都道府県すべてに設置されており、働き方改革に関連する相談を総合的に受け付けてくれます。
来所・電話・メールでの相談が可能で、企業への専門家派遣も3回まで無料です。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。







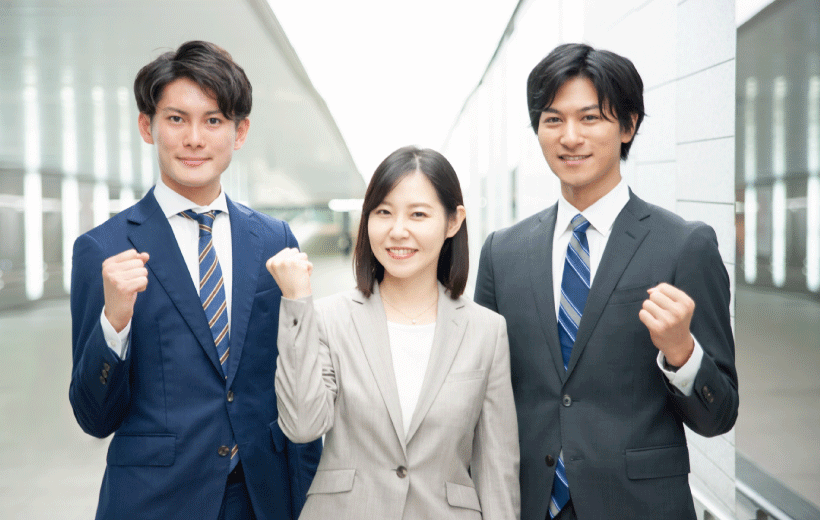
コメント